日本株 vs 外国株 – 本当にお得なのはどっち?

皆様、投資を始めようと考えている方や、すでに投資を行っている方にとって、「日本株と外国株、どちらに投資すべきか」という疑問は尽きないものです。特に昨今の世界経済の変動や円安の影響もあり、資産形成の選択肢として両者の違いを理解することは非常に重要になっています。
このブログ記事では、日本株と外国株のリターン比較、税制や手数料の違い、そして過去10年のパフォーマンスから見える将来性について、投資初心者の方にもわかりやすく解説していきます。松くわ証券サービスの長年の実績と知識を基に、あなたの資産形成に最適な投資先をご提案します。
投資判断に悩んでいる方も、これから投資を始める方も、この記事を読めば日本株と外国株の違いが明確になり、自分に合った投資戦略を見つけることができるでしょう。それでは、日本株と外国株、本当にお得なのはどちらなのか、詳しく見ていきましょう。
1. 日本株・外国株、投資リターン徹底比較!あなたの資産形成に最適なのはどちら?
資産形成を考える上で避けては通れないのが「日本株」と「外国株」の選択です。長期投資でどちらが有利なのか、多くの投資家が頭を悩ませる問題でしょう。まずは両者のリターン実績を見てみましょう。日経平均株価の長期リターンは年率約3〜4%程度である一方、米国S&P500指数は年率約10%前後の成長を見せています。この数字だけを見ると外国株、特に米国株が圧倒的に有利に思えますが、そう単純ではありません。
為替リスクという大きな要素が存在します。円安になれば外国株の円換算リターンは上昇しますが、円高になれば目減りします。過去10年間は円安傾向が続いたため、米国株投資は為替の後押しも受けて好調でした。しかし歴史的に見れば、為替は循環するもの。このリスクをヘッジするためには、日本株と外国株のバランス良い保有が賢明です。
また配当利回りも重要な比較ポイント。日本企業の平均配当利回りは約2.5%前後で、米国企業の平均約1.5%を上回る傾向にあります。特にTOPIX高配当指数に連動するETFなら4%前後の配当が期待できます。インカムゲイン重視の投資家には日本株の魅力が高いと言えるでしょう。
さらに見逃せないのが業種の偏り。日本株は製造業や金融業が中心である一方、米国株はテクノロジー関連の比率が高くなっています。つまり、両方に投資することで業種分散も自然と図れるのです。
最適な選択は「どちらか」ではなく、自分の投資目標やリスク許容度に合わせた「両方の適切な配分」にあると言えるでしょう。長期的な資産形成を考えるなら、世界経済の成長を取り込める外国株と、身近で為替リスクのない日本株、双方をポートフォリオに組み入れることが王道と言えます。
2. 知らないと損する「日本株と外国株」の税制と手数料の違い – プロが教える賢い選び方
投資を始める際に直面する大きな選択肢が「日本株」と「外国株」です。どちらを選ぶかで税金や手数料が大きく変わってくるため、知識不足のままでは思わぬ損をすることも。このパートでは両者の決定的な違いを徹底解説します。
まず税制面から見ていきましょう。日本株と外国株はともに売買益・配当金に対して20.315%の税率が適用されます。しかし、ここで見逃せないのが「外国税額控除」の存在です。米国株などは現地で10%程度の源泉徴収税が差し引かれますが、この税金は日本での確定申告により一部取り戻すことが可能です。この手続きを知らずに放置している投資家は少なくありません。
手数料については、一般的に外国株の方が高めに設定されています。例えば大手ネット証券のSBI証券では、日本株の取引手数料は数百円から0.1%程度ですが、米国株では最低5ドル程度から取引額の0.45%前後が必要です。さらに、為替手数料も上乗せされるため、小額投資では影響が大きくなります。
また見落としがちなのが「為替リスク」です。外国株は円安で含み益が増える一方、円高では目減りします。楽天証券やマネックス証券などでは外貨建て株式を購入できるだけでなく、外貨預金や外貨MMFなどで為替リスクに対応する選択肢も提供しています。
投資スタイルに合わせた選び方としては、長期・分散投資志向なら手数料の安いインデックスETFを、短期売買志向なら流動性の高い日本株を中心にするといった方法があります。野村證券やみずほ証券などの対面証券会社では、こうした個別のアドバイスも受けられます。
賢明な投資家は、税制や手数料の仕組みを理解した上で、自分の投資額や期間に合わせた選択をしています。単純に「どちらがお得」ではなく、自分の投資スタイルに合った選択をすることが重要なのです。
3. 過去10年のパフォーマンスから読み解く!日本株と外国株、将来性が高いのはどちらか
過去10年間の日本株と外国株のパフォーマンスを比較すると、明確な差が見えてきます。S&P500指数は過去10年で約250%の上昇を記録したのに対し、日経平均株価は約120%の上昇にとどまっています。この数字だけを見れば、外国株、特に米国株が圧倒的に有利に思えるでしょう。
しかし、最近の日本株市場にも注目すべき変化が起きています。日銀の金融政策転換やコーポレートガバナンス改革の進展により、日本企業の収益性や株主還元への姿勢が改善。実際、TOPIX配当利回りは米国主要指数を上回る水準で推移しています。
また、セクター構成にも大きな違いがあります。S&P500はテクノロジー企業の比率が30%以上を占めるのに対し、日経平均は製造業や金融セクターの比率が高く、近年のAIブームなどの恩恵を受けにくい構造でした。しかし、この構造的な違いは今後のローテーション相場では日本株に有利に働く可能性もあります。
為替の影響も重要なポイントです。円安局面では外国株投資の円換算リターンが大きく上昇しますが、逆に円高になれば目減りするリスクがあります。実際、直近数年の米国株パフォーマンスの一部は円安効果によるものでした。
地政学的リスクの観点では、米中対立や各国の保護主義的な政策により、グローバルサプライチェーンの再構築が進む中、日本企業の技術力や信頼性が再評価される可能性があります。半導体関連材料や精密機器など、特定分野での日本企業の競争力は依然として高いことも忘れてはなりません。
結論として、過去10年のパフォーマンスだけで将来性を判断するのは危険です。投資環境は常に変化しており、現在の日本株には割安感があるとの見方も強まっています。分散投資の観点からも、日本株と外国株をバランスよく保有し、定期的な見直しを行うことが長期的な資産形成には重要といえるでしょう。






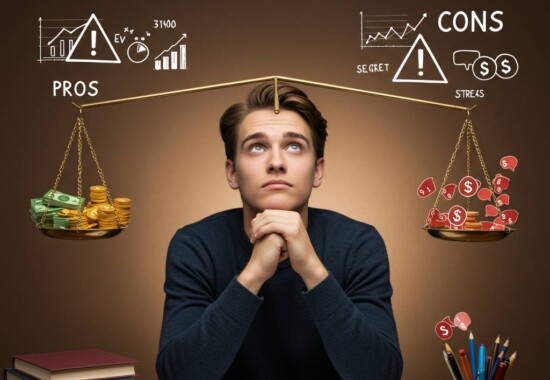





この記事へのコメントはありません。